犬の虫除けスプレーで手作りと検索する飼い主さんは、愛犬の体への影響を心配し、安全な虫除け対策を探しているのではないでしょうか。
この記事では、ヒバやレニームなど天然素材を使ったおすすめの作り方を紹介します。
オーガニックな成分を選べば、舐めても大丈夫な配合が可能になり、子犬や敏感肌の犬にも安心です。
また、ハッカ油スプレー 作り方のポイントや、マダニにも対応できる精油の選び方も解説します。
実際に使用している方々の口コミも交えながら、必要な材料、安全に使うための注意点まで丁寧にお伝えします。
手作りスプレーで、愛犬に優しい虫除け対策を始めてみませんか。
■本記事のポイント
- 安全性に配慮した虫除けスプレーの作り方
- ヒバやレニームなど天然素材の活用方法
- 舐めても大丈夫な配合や使い方の注意点
- マダニ対策に効果的な精油の選び方
犬の虫除けスプレーを手作りで安全な対策

市販の虫除けスプレーには便利さがありますが、添加物や化学成分が気になる飼い主さんも多いのではないでしょうか。
特に皮膚が敏感な犬や、子犬・高齢犬にとっては、安全性に十分配慮した対策が求められます。
そこで注目されているのが、天然素材を使った手作り虫除けスプレーです。
自然由来の成分で作れば、成分を把握でき、愛犬にも安心して使えます。
ここでは中でも人気の高い「ヒバ」や「オーガニック素材」などを取り入れた作り方や効果をご紹介します。
ヒバを使ったスプレー材料と効果

前述のとおり、天然素材であるヒバ油を用いた虫除けスプレーは、犬にも比較的安全とされます。
市販のヒバ油は、青森ヒバから抽出された精油で、ヒノキに似たウッディーな香りが特徴です。
主成分のヒノキチオールやシトロネロール、リナロールなどが高い抗菌・防虫力を発揮します。
用意する材料は、ヒバ油、無水エタノール、精製水、スプレーボトルだけです。
配合例としては、水100mlにヒバ油を2~3滴加える、あるいは水45ml+エタノール5mlにヒバ油10~20滴という方法があります。
使用前にボトルをよく振る必要があり、水と油は分離しやすいためです。
また保存期間は防腐剤を含まないため冷暗所で1週間から2週間以内に使い切るのが望ましいとされます。
効果面では、蚊・ダニ・ゴキブリ・蜘蛛など幅広い害虫を寄せ付けず、消臭・殺菌効果も期待できます。
ブラッシングスプレーや耳ケア、寝具・ゴミ箱の除菌にも使え、特に皮膚炎の改善に役立ったケースも報告されています。
ただし顔にはスプレーしないよう注意が必要であり、香りが強いため犬によっては刺激になることもあります。
また使用時は少量から始めてアレルギー反応を確認し、異常があればすぐに中止し獣医師に相談する必要があります。
オーガニック素材で作る虫除け
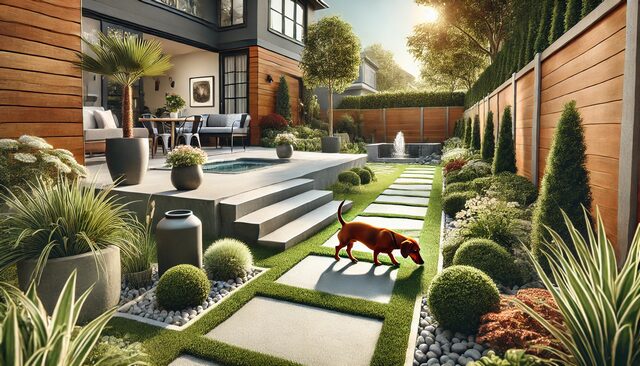
オーガニック素材を使った虫除けスプレーは、化学合成成分を避けたい飼い主さんにとって魅力的です。
例えばシトロネラ、レモングラス、ユーカリ、ゼラニウムなど自然由来のエッセンシャルオイルは、犬にも比較的低刺激で使いやすい成分として注目されています。
一般的な作り方は、無水エタノール5から10ml、精製水90から95mlに虫除け効果のある精油を10から20滴加える方法です。
例えば100ml容器ならエタノール10ml+精油20滴+精製水90mlという構成で調整できます。
濃度は約0.25から0.3%程度の非常に低刺激レベルに設定されており、特に子犬や敏感肌の犬にも適しています。
香りの選択肢によって、虫の種類や犬の好みに合わせて調整可能です。
たとえばレモングラスはシトラール含有率が高く、蚊やダニに強く効く一方、ゼラニウムはシトロネロールが25から40%含まれ、香りと虫除け両方のバランスが優れています。
使い方としては、スプレー前に容器をよく振り、顔回りには直接噴霧しないようにし、飼い主が手にスプレーしてから塗布します。
揮発性が高いため、効果を持続させたい場合はこまめに再スプレーするのが効果的です。
デメリットには、保存期間が短く、防腐剤なしで2週間程度で使い切る必要がある点や、犬が舐めた場合に刺激になることもあるため、使用後の観察が重要です。
また猫との併用は避ける必要があります。
レニームを取り入れた手作り配合

前述のとおり、レニーム(ニーム抽出物)を活用した手作り虫除けスプレーは、天然由来の成分だけで構成されるため犬への刺激が少なく、安全性が高いとされています。
ニームオイルにはノミ、マダニ、蚊を寄せ付けない強い忌避効果があり、さらに皮膚や被毛にも潤いを与える性質があります。
用意する材料は、ごくシンプルです。
ニームオイル(またはレニーム製品)、天然乳化剤としてのムクロジエキス、精製水だけで構成されます。
化学防腐剤や合成界面活性剤は一切使わない点が特徴です。
手作りする際は、まずニームオイルを精製水とよく混ぜ、必要に応じて少量の天然乳化剤(ムクロジエ)を使用して安定化させます。
エタノールを使わなくても自然成分だけでエマルジョンタイプのスプレーができます。
保存期間は市販より短くなるため、2週間以内を目安に使い切るのがおすすめです。
実際の使い方としては、散歩前やシャンプー後にボトルをよく振って全身に噴霧し、特に毛が薄い腹部や脚の先にもしっかりなじませます。
被毛やマット、ケージにも使用することで、ノミやダニの侵入を抑止できます。
注意点として、天然成分とはいえ成分が強く感じられる場合もあるため、初めて使う際には少量で様子を見てから正常に皮膚や被毛になじむか確認してください。
また、傷口や目・耳まわりにはスプレーしないことが望ましいです。
マダニにも対応できる配合のポイント

多くは、マダニは草むらや湿地帯に多く生息し、犬に侵入すると深刻な健康リスクをもたらします。
このため、手作り虫除けスプレーにもマダニ対策が重要です。
マダニ対策には、ニーム(レニーム)だけでなく、シトロネラやユーカリ、ティーツリーのような天然エッセンシャルオイルを併用することで忌避率が高まります。
具体的な配合ポイントとしては、ニームオイルをベースに、シトロネラ精油を数滴から10滴程度(精製水100mlあたり)加えるとよいでしょう。
相乗効果で虫が嫌がる香りのバランスを整えることで、マダニ対策にも対応可能になります。
ティーツリーやユーカリレモンを少量足すと、さらに防虫スペクトラムが広がります。
使用方法としては、スプレー後に30~40cmほど離して噴霧し、特に前足・後ろ足・お腹・首の付け根などダニが付着しやすい部位に重点的に吹きかけてください。
洗濯後や雨で濡れた場合、再度スプレーすることで効果を維持できます。
デメリットには、精油を併用することで香りが気になる犬もいる点や、長時間直射日光下では香りの成分が揮発しやすい点があります。
さらに、多様な精油を混ぜることでアレルギー反応が起こる可能性もあるため、少量から始めて様子を見ながら使うことが大切です。
初回は犬の顔周りには避け、手にスプレーしてから優しく触れるなど慎重に行ってください。
犬の虫除けスプレーで手作りの作り方と注意

犬の虫除けスプレーを手作りする際には、材料を揃えるだけでなく、安全に使うための基本的な知識が欠かせません。
特に、ハッカ油のように扱いに注意が必要な精油や、愛犬がスプレーを舐めてしまった場合のリスクなど、意外と見落としがちなポイントもあります。
また、子犬や持病のある犬に使えるかどうかも気になるところです。
ここでは、手作りスプレーを安心して使い続けるための具体的な注意点や、使用頻度、保存方法、実際の飼い主からの口コミなどを詳しく紹介します。
ハッカ油スプレーの作り方と希釈注意

ハッカ油を使った虫除けスプレーは、材料が非常にシンプルで家庭でも簡単に作れます。
無水エタノール10mlにハッカ油を10から20滴ほど加えてよく混ぜ、その後精製水(または清潔な水)90mlを加えて再び振ります。
水と油は分離しやすいため、使用前にも必ず容器を振ってから使ってください。
容器はハッカ油が溶かしてしまう素材(ポリスチレンなど)を避け、ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス製がおすすめです。
注意点として、ハッカ油は濃度が高すぎると犬の皮膚に刺激を与えるおそれがあります。
特に子犬や敏感肌の犬、妊娠中の母犬には刺激が強すぎるため避けた方がよいでしょう。
初回はハッカ油を3から4滴程度に抑え、愛犬の様子を見ながら少しずつ調整するのが安心です。
保存期間は防腐剤を含まないため、冷暗所で1週間から10日程度が目安です。
香りが薄れてくると虫除け効果も減少しますので、必要に応じて使い切るか、都度調整しながら作り替えて使用することが望ましいです。
顔周りや目の近くは避け、手にスプレーしてから優しくなでて塗るなど、刺激を抑えながら使いましょう。
舐めても大丈夫な配合基準

犬がスプレー箇所を舐めても大丈夫な配合にするには、主に天然由来成分を使用することが基本です。
特にレニーム(ニーム)をベースにしたスプレーは、精製水とニームオイル、天然乳化剤(ムクロジ)だけで構成され、安全性が高く評価されています。
これにより、万一舐めても体に問題が起こりにくい設計です。
市販でも「舐めても安心」と謳う製品が複数あり、FLFやA.P.D.C.、mofuwaなどは、乳幼児やペットの健康基準をクリアした成分で作られています。
これらに共通するのは、合成防腐剤や化学成分(ディート、ピレスロイドなど)を使わず、天然オイルや水溶性成分のみで構成されている点です。
使用上の目安としては、濃度を低く(例えば全体100mlに対してオイル成分が数%以内)抑えることが肝要です。
濃すぎる場合は、犬が舐めた際に刺激や胃の不調を起こす可能性があります。
また使用後には様子を観察し、かゆみや皮膚の変化がないか確認してください。
猫がいるご家庭では使用を避けること、また犬でも少量でテストしてから使用するのが安全です。
これらの配慮を守れば、舐めても概ね安全な虫除けスプレーが手作りできます。
子犬や持病犬への安全性

子犬や持病がある犬には、敏感な体に配慮した配合が不可欠です。
一般的な市販スプレーには化学成分(ディートやピレスロイドなど)が含まれることがあり、これらは子犬や免疫が弱い犬にとって刺激となる恐れがあります。
しかし天然素材(精油ベースなど)で自作すれば成分を明確にでき、低濃度の希釈で使用すれば比較的安全です。
例えば精製水100ml+無水エタノール10ml+精油8~10滴という構成なら、敏感な皮膚に対しても安心感があります。
一方で、妊娠中の犬や持病のある犬では個別の状態によって異なるため、利用前に獣医師に相談することが望ましいです。
初回使用時は足先などの部分に少量を試し、24時間ほど経って皮膚の状態(赤み、かゆみ、脱毛など)に問題がなければ徐々に適用範囲を広げるとよいでしょう。
スプレー使用は必要?頻度と保存

手作り虫除けスプレーは自然成分による防虫効果が魅力ですが、揮発性が高く効果の持続時間には限りがあります。
例えば屋外で散歩の前に使用するのが基本ですが、2~3時間おきにスプレーし直すことで防虫効果を維持できます。
また室内やケージなど空間に使用する場合、こまめに再噴霧することでノミやダニの侵入予防に役立ちます。
保存面では、防腐剤を使わないため冷暗所で保管し、1~2週間以内には使い切ることが望ましいです。
白濁や異臭が出た場合は使用を中止し、新しく作り直してください。
特に精製水よりも水道水は劣化しやすいため、できれば精製水を使うとより安心です。
安全性の口コミ評価を紹介

多くの飼い主やレビューでは、天然成分のみで作られたスプレー(特にレニームやオーガニック精油ベース)の安全性が評価されています。
実際、ある口コミでは「天然成分100%で匂いも控えめ。
愛犬が嫌がらず舐めても安心して使えている」との声があります。
また「蚊やダニ、マダニに効果があった」「キャンプ中も蚊に刺されなかった」など、忌避力に関する評価も好印象です(レニーム製品など)。
ただし、中には香りが好みでない、精油の香りが強すぎると感じるユーザーもいて、個体差への配慮は必要です。
口コミ全般からは、「化学成分なし」「舐めても身体に害がない」「敏感肌にも使える」など、安全性重視の評価が多く寄せられています。
【まとめ】犬の虫除けスプレーで手作りについて
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。
- 市販品の添加物が気になる飼い主には手作りが適している
- ヒバ油は防虫・殺菌・消臭に効果がある天然素材である
- ヒバ油は香りが強く犬によっては刺激になることがある
- オーガニック精油は低刺激で初心者にも扱いやすい
- 精油の濃度は0.25から0.3%程度に抑えるのが安全
- レニームはニームオイルを基にした天然虫除け素材である
- レニーム配合スプレーは皮膚や被毛の保湿効果もある
- マダニ対策にはシトロネラやユーカリなどの精油が有効
- 使用時は顔を避けて手に取って塗布するのが基本
- ハッカ油は濃度が高すぎると刺激になるため希釈が必要
- 舐めても大丈夫な配合は天然成分と低濃度が前提となる
- 子犬や持病犬には個別の体調に応じた配慮が求められる
- 効果持続のためには2から3時間ごとの再スプレーが理想
- 保存は冷暗所で1から2週間を目安に使い切るべきである
- 安全性に関する口コミでは天然素材への満足度が高い


