新幹線にペットを連れて移動する際、「ペットキャリー 新幹線」で検索しても情報がバラバラで分かりにくいと感じたことはありませんか?
特に初めての利用では、「新幹線でペットをどこに置くべきですか?」「新幹線で犬を個室にできるのか?」といった疑問が次々に浮かぶものです。
この記事では、「新幹線にペットを連れて乗るには?」という基本的なルールから、キャスター付きや犬 キャリーリュック、猫用ケースなどの使いやすさを比較し、人気の高い「ペチコ」などのおすすめ商品も紹介しています。
また、車内での適切な置き場所や、犬を新幹線に5時間乗せても大丈夫かといった実用的な視点からも解説しているので、ペットと安心して移動したい方はぜひ最後までご覧ください。
キャリーの大きさや重量制限も含め、新幹線での快適なペット移動を叶えるヒントが満載です。
■本記事のポイント
- 新幹線にペットを乗せるための基本ルール
- ペットキャリーの大きさや重さの規定
- 手回り品きっぷの購入方法と注意点
- 新幹線に適したおすすめキャリーの種類
ペットキャリーを新幹線での基本ルール

新幹線にペットを同伴する場合、「キャリーに入れればOK」と思っていませんか?実は、各鉄道会社には細かい規定があり、それを守らなければ乗車を断られることもあります。
知らずに乗車するとトラブルになる可能性もあるため、事前の確認がとても重要です。
ここでは、手回り品きっぷの取得方法や、車内でのペットの置き場所に関するルールなど、愛犬・愛猫との快適な新幹線移動を実現するために押さえておくべき基本ルールを詳しく解説します。
新幹線にペットを連れて乗るには?

新幹線に小型犬や猫などのペットを同伴する場合は、「手回り品きっぷ」を購入し、規定を守る準備が必要です。
まず、動物専用のキャリーに全身が収まり、顔が外に出ないように閉じておくことが求められます。
ペットは「荷物」として扱われるため、スリングや抱っこでは持ち込めません。
手回り品きっぷは1頭(1つのペットケース)につき290円で、乗車当日に駅の有人改札口や窓口で現金による購入が必要です(自動券売機では購入不可)。
購入時には、ケースを駅員に見せて持ち込み可能な状態か確認を受ける必要があります。
タグ型のきっぷをケースに付け、係員から提示を求められた際に見せましょう。
足元や荷物置き場など座席上ではなく、指定のスペースにキャリーを置いて利用します。
ペット用の座席を購入することはできませんし、ケースから出すことも禁止されています。
ペットキャリー大きさと重さ制限

ペットキャリーには明確なサイズと重量の制限が定められています。
まず、縦・横・高さの合計が120cm以内でなければなりません。
これはキャリー本体+犬や猫の体がすっぽり収まるものに限ります。
次に、キャリーとペットを含めた総重量が10kg以下である必要があります。
重量オーバーの場合は持ち込み不可になるため、軽量な素材やケース選びが重要です。
なお、ペットカートやバギーはケースと車輪・取っ手等が分離できるものなら条件を満たせる場合があります。
ただし、固定式のカートは全体が規定を超える可能性が高いため注意しましょう。
ケースに顔が出ていたり、布製で形が固定されないもの(ドッグスリングなど)は規定外とされ、持ち込み不可となります。
これは安全や他の乗客への配慮から定められており、形状にも注意が必要です。
手回り品きっぷの取得と注意点
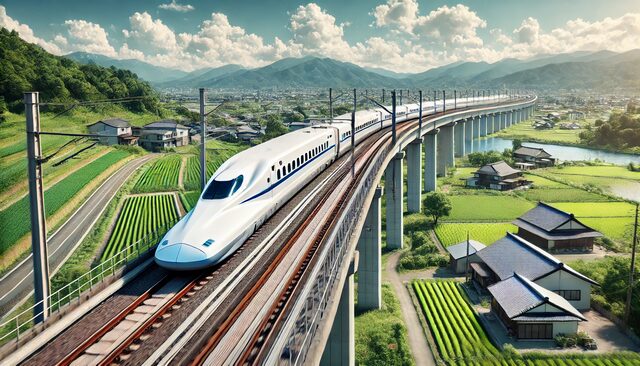
新幹線でペットを連れて乗るには、まず「普通手回り品きっぷ」の取得が必須です。
これはペットを荷物扱いとする制度で、ペットケース1つにつき290円です(購入は現金のみ、自動券売機不可)。
たとえ同乗者がいても、オンラインでの事前購入はできず、乗車当日に駅改札か窓口で係員にケースを見せて購入しなければなりません。
当日は、係員がケースが指定サイズ・形状を守っているか確認します。
問題なければ、タグ型のきっぷを発行し、ケースに取り付けるか携帯します。
提示を求められた際にはすぐに見せられるようにしておきましょう。
持ち込み可能な手回り品は、身の回り品を除き2つまでです。
これはペットケースも含みますが、例外的に同一ケースに複数匹を入れることは可能です。
ただし、総重量が制限(10kg以内)を超えないよう注意が必要です。
さらに、ケースからペットを車内で出すことは禁止されています。
他の乗客への配慮として、ケースは足元か指定の荷物スペースに置き、決して座席や網棚には置かないようにしてください。
また、混雑している時期や状況によっては、持ち込みを断られる可能性もあります。
新幹線で犬を個室スタイルに置く方法
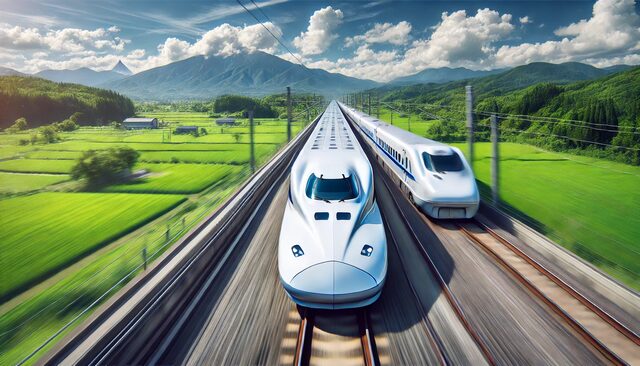
新幹線では犬用の座席を購入することはできません。
そのため、いわゆる「個室」に犬を置くという方法も原則として認められていません。
多目的室は存在しますが、基本的に障がい者や高齢者、授乳など特定の目的に使用されるものであり、ペット同伴利用はマナー違反と見なされます。
そのため、犬を連れて乗車する場合は、あくまで自身の席の足元や車両最後部の荷物スペースにキャリーを置き、ケースから出さずに利用する形式になります。
これが「個室スタイル」に近い状況と捉えることもできますが、実際には個室利用ではありません。
ただし、混雑時以外で、デッキや多目的スペースに空きがあり、かつ利用目的に合致する場面であれば、車掌にお願いして一時的に多目的室を使わせてもらえる可能性があります。
ただし、犬をケースから出す行為は厳禁です。
また、本来の目的の利用者が現れた場合はすぐに譲る必要があります。
出入口付近の通路側座席を選ぶと、トラブル時に移動しやすく、ペットの足元のケース管理もしやすくなるためおすすめです。
ペットキャリーは新幹線おすすめと注意点

新幹線にペットを連れて行くなら、キャリー選びはとても重要です。
ペットが安心して過ごせることはもちろん、サイズや機能が新幹線の規定に適合しているかも確認しなければなりません。
ここでは、よく使われているキャリータイプの比較や、実際に新幹線で使いやすいと評価されているおすすめキャリーを紹介します。
犬・猫それぞれに適した選び方のポイントも詳しく解説していますので、自分のペットに最適な一台を選ぶ参考にしてください。
キャスター付きキャリーは新幹線でも使える?

キャスター付きのペットキャリーは、取り扱い方法を正しく理解すれば新幹線でも利用可能です。
主に4wayキャスター付きのリュック型やハードケースタイプがあり、折りたたんでケースのみを規定サイズ内に収まるようにすれば持ち込み可能です。
ただし、運搬用のキャスターや取っ手は基本的に取り外すか折りたたみが必要で、分離できないタイプではサイズオーバーとなり持ち込み不可になることがあります。
多くの製品では本体サイズがタテ・ヨコ・高さの合計114?120cm以内に設計されており、新幹線の規定(120cm以内、重さ10kg以内)に対応しています。
たとえば、幅41×高43×奥行30cm、重量2kg程度のキャスター付きバッグは実際に許容された事例があります。
つまり、正しく設計されているキャリーやバッグであれば、新幹線の制約をクリアできます。
その中には大型の小型犬にも対応できるものがあり、乗り物での移動時にはキャスターが便利です。
ただし、購入時には取っ手が折れ曲がるか、キャスターが簡単に外せる製品を選ぶことが重要です。
使用前には必ずサイズと重量を測定し、乗車時に駅員に確認してもらうようにしてください。
ペチコ入りキャリーは何?メリットとは

「ペチコ(PETiCO)」は日本発のペットキャリーブランドで、スーツケースメーカーが開発したハードタイプのキャリーケースです。
移動時に引いて運べるキャスターや、高度なストッパー機能を備えており、電車や新幹線での使用に向いています。
多くのモデルでは中型犬でも使えるサイズ(Mサイズなら耐重量13kg、Lサイズは18kgまで)に対応しつつ、ポリカーボネート製で軽量・丈夫です。
さらに、キャスターを固定できる機能があるため、駅や休憩中に「迷子ハウス」として活用できる点も便利です。
公共交通機関の規約に応じて使える設計になっています。
実際の利用者の声によれば、Lサイズでも足元に置けるケースの製品があり、9kgの柴犬でも問題なく新幹線に持ち込めた例があります。
駅員によってサイズ確認を受けて手回り品きっぷを取得し、乗車できたとの報告も複数あります。
つまり、ペチコは新幹線の規定内に収まるサイズ設計と実用性が両立しており、初心者にも安心して使える選択肢です。
ただし注意点として、サイズギリギリの場合、座席後部の足元スペースや進行方向の端に置く必要があり、座席によってはリクライニングと干渉する場合があります。
特に進行方向前方または後方の席を選ぶとスペースの余裕が得られやすいので、乗車前に座席位置の確認と相談を行うことをおすすめします。
犬のキャリーリュックと猫用ケースの比較
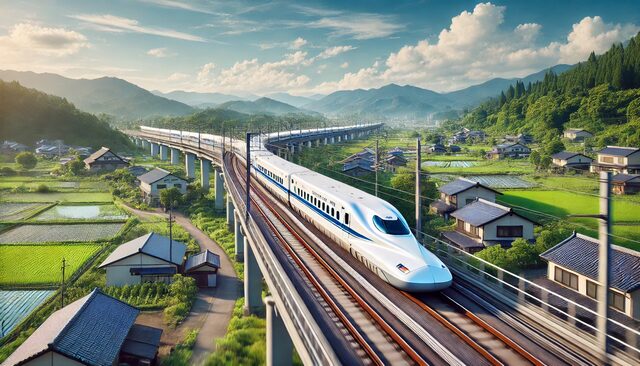
犬用のキャリーリュックと猫用ケースには、それぞれの用途や性質に応じたメリットと注意点があります。
犬のキャリーリュックは背負える形状が多く、両手が自由になる点が大きな強みです。
地下鉄や徒歩での移動にも適しており、サイズがコンパクトなモデルであれば新幹線の規定(縦・横・高さの合計120cm以内、重さ10kg以内)に収まるものもあります。
一方で、リュック型は横幅が狭く、伏せたり体を回転させる余裕が少ないため、中で過ごしにくい場合があります。
猫用ケース(ハードケースタイプ)は、プラスチックなどの素材で形がしっかりしており、通気性や脱走防止に強く、移動中も安定しています。
ただし重さがあるモデルだと荷物の重量制限に引っかかることもあり、持ち運びにはリュックより疲れるかもしれません。
比較すると、徒歩や混雑の中を移動するならリュック型が有利で、安定性とペットの快適性を重視するならハードケースが安心です。
それぞれの用途やペットの性格、移動経路に合わせて選ぶことが重要です。
愛犬・愛猫におすすめペットキャリー

愛犬・愛猫との新幹線移動には、規定サイズ内で快適性と安全性を両立できるキャリーを選びましょう。
まず、ソフトタイプでは通気性や軽量な素材を活かしたモデルが使いやすく、折りたたみ・肩掛け・手提げが可能な2WAY~3WAYタイプがおすすめです。
たとえば、4way仕様で底面がしっかりしている「Pet Carrier muna CS」は、電車移動に配慮された構造で足腰の負担も軽減できる点が好評です。
また、初心者でも使いやすい猫用リュックとして人気の「PLEISE ペットキャリーバック」は、上部が100度以上開き出し入れが簡単で、飛び出し防止リードもついているため安心です。
これらはいずれも新幹線のサイズ・重量制限をクリアでき、かつ日常利用にも耐える設計となっています。
ただし、素材や耐荷重を確認し、ペットが十分に回転できる広さや脱走防止機構が備わっているかチェックすることが大切です。
また、重量がギリギリの場合は係員に事前確認を行うことをおすすめします。
【まとめ】ペットキャリーを新幹線について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。
- ペットの新幹線乗車には手回り品きっぷが必要
- 手回り品きっぷは当日駅の窓口で購入する
- キャリーは縦・横・高さの合計が120cm以内
- ペットとキャリーの総重量は10kg以内
- 顔が出る構造やスリング型は持ち込み不可
- キャリーは足元か荷物置き場に置くのが基本
- ペット用の座席購入はできない
- 多目的室の使用は原則不可で例外的な対応のみ
- キャスター付きキャリーは取り外しできれば使用可能
- ペチコは新幹線に対応した設計のハードケース
- キャリーリュックは犬の移動に便利だが狭さに注意
- 猫用ハードケースは安定性があり脱走防止に適している
- ソフトキャリーは軽量で通気性がよく扱いやすい
- ケース選びは移動時間やペットの性格に応じて選ぶ
- 混雑時は持ち込み制限される可能性があるため事前確認が重要


