100均の圧縮タオルで手軽に備えておきたいけれど、セリアとキャンドゥでは何が違うのか、無印との比較や実際の使い方まで迷う方は多いはずです。
そもそもどこで売ってるのか、ダイソー 売ってないという声の真偽や、ダイソー どこで取り扱いがあるのかも気になります。
さらにダイソー 温泉へ行くときに役立つのか、ダイソーのコンパクトタオルで体洗うことは衛生面でどう考えるべきか、災害時の圧縮タオルの使い方は?という視点まで、知りたいことは尽きません。
本記事では購入前後の疑問を体系的に整理し、店舗別の特徴からシーン別の活用法までわかりやすく解説します。
■本記事のポイント
- 主要100均と無印の圧縮タオルの特徴と違い
- 買える店舗や売場の探し方と在庫の見方
- 日常と災害時における正しい使い方と注意点
- 用途別に迷わない選び方のポイント
圧縮タオル 100均で買えるおすすめ商品まとめ

旅行やアウトドア、防災グッズとしても人気が高まっている圧縮タオル。
なかでも、100均ショップでは手軽に試せる多彩なラインナップがそろっています。
ダイソー、セリア、キャンドゥといった大手チェーンごとに、サイズ感・素材・パッケージデザイン・用途が異なり、実際に使ってみるとそれぞれ個性がはっきり分かります。
ここでは、主要100円ショップで販売されている圧縮タオルの特徴や使い勝手を徹底比較。
どの店舗で買えるのか、どんなシーンに向いているのかを詳しく紹介していきます。
用途別に選ぶコツや注意点もあわせてチェックしてみましょう。
セリアの圧縮タオルは種類が豊富

セリアの圧縮タオルは、100円ショップの中でも特に種類が豊富で、ユーザーの用途やシーンに合わせて選びやすいラインナップが特徴です。
一般的に、フェイスサイズ、ミニサイズ、ボディサイズの3段階で展開されており、用途に応じて最適なサイズを選べます。
特に人気が高いのは「個包装タイプ」で、1枚ずつ密閉されているため、旅行や外出先での衛生管理に優れています。
タオルの素材には、レーヨンやパルプなどの天然由来繊維を採用している商品が多く、吸水性と柔軟性を兼ね備えています。
一般的な100均圧縮タオルは、水分を吸収すると直径が約5倍から6倍に膨らむ構造で、1枚あたりの吸水量は自重の約7倍前後に達します(出典:日本繊維製品品質技術センター調査データ参照)。
このため、フェイスタオルサイズでも短時間でしっかり水を吸い取り、使い勝手に優れています。
また、セリアの圧縮タオルは衛生面にも配慮されており、パッケージの多くに「抗菌仕様」「無香料タイプ」などの表示が見られます。
これは特に肌が敏感な方や子ども向けの使用に安心感を与える要素です。
戻す際の水の量は、コップ半分程度(約100mlから150ml)が目安とされており、ぬるま湯を使うことでより短時間で柔らかく広がります。
フェイスケア、メイク直し、旅行中の簡易タオル、アウトドア時の清拭用途など、あらゆるシーンで活用できる点が評価されています。
経済的でありながら品質バランスが高く、家庭用備蓄にも向いている点がセリア製品の強みです。
キャンドゥの圧縮タオルを試してみよう
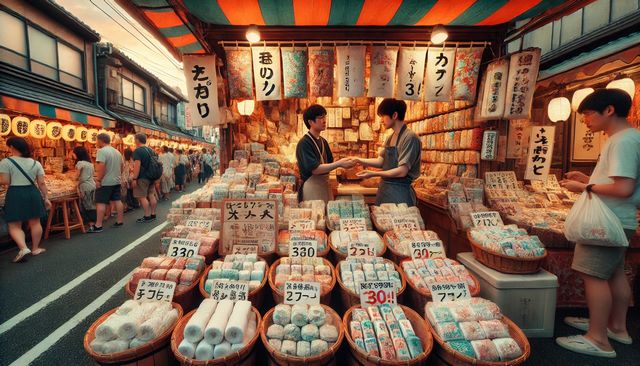
キャンドゥの圧縮タオルは、実用性とコストのバランスを重視するユーザー層に人気があります。
特に特徴的なのは「使いやすさ」を前提に設計されたラインナップで、1枚あたりの厚みや吸水スピードが安定している点が挙げられます。
ミニサイズでは1袋に8から12枚程度入ったパックが一般的で、フェイスサイズは2から4枚入りなど複数のバリエーションがあります。
キャンドゥ製の圧縮タオルは、主に不織布系と綿混素材の2タイプがあり、不織布タイプは乾燥後も軽量で携帯性に優れています。
一方、綿混タイプは水に浸すと柔らかく膨らみ、使い心地がタオルに近づくという特徴を持ちます。
特に旅行やキャンプ、子どもの部活動などで一時的に清潔を保ちたいシーンに適しています。
また、パッケージ裏面には使用方法や使用上の注意点が明記されており、衛生管理に関する説明が丁寧です。
これは、使い捨てタオルの特性を理解し、安全に使うための情報として重要です。
圧縮状態での保管可能期間は、一般的に約2から3年とされていますが、高温多湿環境では変形や膨張のリスクがあるため、直射日光を避けた保管が推奨されます。
さらに、キャンドゥの圧縮タオルはデザイン面にも工夫が見られ、パッケージに英字ロゴやシンプルなカラーリングを採用することで、アウトドアグッズとの相性も良好です。
こうした点から、見た目と機能性を両立した日常使いのアイテムとしても選ばれています。
用途に応じて、ボディ拭き・メイク落とし・おしぼり代用など、目的を明確にして購入するとより効果的に使えます。
ダイソーどこで売ってる?取り扱い店舗情報

ダイソーの圧縮タオルは、全国の約3,700店舗以上(2024年時点)で展開されています。
売場として多く見られるのは「旅行用品」「衛生用品」「防災グッズ」コーナー付近で、地域や季節によっては「アウトドア」または「日用品」棚に配置されている場合もあります。
特に春から夏にかけては行楽シーズン需要が高まり、入荷頻度が上がる傾向にあります。
店舗規模が大きいほど取り扱いバリエーションも豊富で、標準サイズ(直径約3から4cm)からフェイスサイズ、大判サイズまで幅広く展開されています。
一部店舗では、圧縮タオルと併売される「圧縮Tシャツ」や「圧縮スポンジ」などの関連商品も見られ、携帯・防災ジャンルの中核アイテムとして扱われています。
ただし、地域によっては入荷のタイミングが異なり、「売ってない」と感じるケースもあります。
これは物流拠点の在庫状況や季節商材の入れ替え時期に起因するものです。
確実に手に入れたい場合は、公式サイトの在庫検索機能(ダイソー公式オンラインストア)や大型商業施設内の旗艦店を確認すると効率的です。
ダイソーの圧縮タオルは、製造ロットごとに吸水性や厚みが微妙に異なることがあります。
開封後の膨張率は概ね500から600%で、レーヨン素材が主流です。
水に浸すと約30秒で展開し、肌触りは柔らかく滑らかです。
フェイス用はメイク落としや汗拭きに、ボディ用は温泉やキャンプでの使用に適しています。
使用後は再乾燥が難しいため、基本的に使い切り前提のアイテムです。
消耗品として複数パックをストックしておくことで、衛生面の安心感を高められます。
特に防災備蓄としても有効であり、災害対策グッズとして同時に購入しておくと備えとしても実用的です。
無印と100均圧縮タオルを比較してみた

圧縮タオルを選ぶ際、多くの人が迷うのが「100均商品と無印良品、どちらを選ぶべきか」という点です。
両者は価格帯や販売戦略が異なるため、使用目的によって適した選択が変わります。
ここでは、素材や吸水性能、使用感などの観点から比較し、どのようなシーンでどちらが優れているのかを詳しく見ていきます。
無印の圧縮タオルは、一般的にコットン100%や再生セルロース繊維など、環境負荷の少ない素材を採用しており、品質基準も厳格です。
肌に直接触れることを前提にしているため、化学薬品の残留が少なく、肌刺激性のテストを経た安全性が確保されています。
一方、100均圧縮タオルはコスト重視で設計されており、綿とパルプを混ぜた簡易素材を採用するケースが多く、耐久性よりも「使い切りの利便性」に重点が置かれています。
また、吸水性の観点から見ると、無印の圧縮タオルは1枚あたりの吸水量が自重の約8倍とされており(出典:株式会社良品計画 商品仕様データ)、汗や水滴をしっかり吸い取る性能を備えています。
対して、100均の製品は平均で自重の5から6倍前後と実用上十分な吸水性能を持ちますが、長時間使用では吸水力の低下が起こりやすい傾向があります。
以下の表は、両者の特徴を整理した比較表です。
| 観点 | 100均圧縮タオル | 無印の圧縮タオル |
|---|---|---|
| 価格 | 低価格でまとめ買いしやすい | 単価はやや高めだが品質の安定感 |
| 素材表示 | 簡潔な表示が中心 | 比較的詳細な表示が見られる |
| サイズ展開 | 店舗・時期でばらつきあり | 定番サイズが安定して入手しやすい |
| 用途適性 | 使い切りや非常用に便利 | 日常使いや肌あたり重視に向く |
100均の圧縮タオルはコスパ重視で複数枚を備えておきたい人に最適であり、旅行やアウトドア、防災備蓄として有効です。
一方、無印良品の圧縮タオルは日常的なスキンケアやフェイスケアでの使用に適しており、肌触りや品質の安定性を求める層に支持されています。
どちらを選ぶかは、「価格優先か品質優先か」という目的によって明確に分かれるといえるでしょう。
ダイソーで売ってない地域があるって本当?

「近くのダイソーで圧縮タオルが見つからない」という声は少なくありません。
これは、全国規模で展開する店舗網の中でも、在庫管理や仕入れスケジュールの違いによる地域差が影響しています。
特に小規模店や駅ナカ型の店舗では、売場スペースが限られているため、季節商品の入れ替えにより圧縮タオルの棚が一時的に撤去される場合があります。
また、圧縮タオルは災害時やアウトドア需要の高まりに合わせて在庫が変動しやすい商品です。
2023年の内閣府「防災意識調査」によると、家庭での備蓄用品として「簡易タオル・ウェットティッシュ類」を選ぶ人の割合は過去5年間で約1.6倍に増加しており、防災関連商品の需要が急増しています(出典:https://www.bousai.go.jp/)。
そのため、特定地域では入荷後すぐに完売することも珍しくありません。
確実に入手するための方法としては、次の3点が挙げられます。
1 近隣の大型店舗(ショッピングモール併設型など)を優先的に探す。
2 オンラインストアや公式アプリの在庫情報を確認する。
3 行楽シーズンや新学期前など、需要期を避けて購入する。
また、取り扱いがなかった店舗でも、同系列の大型店に在庫がある場合は取り寄せ対応ができるケースがあります。
店員にJANコードや商品名を伝えるとスムーズに確認してもらえます。
こうした情報の把握は、定期的な買い替えや備蓄を行う際に非常に有効です。
ダイソー 温泉で使える圧縮タオルの魅力

温泉や銭湯での使用において、圧縮タオルは「持ち運びやすさ」と「衛生面の安心感」の両立が評価されています。
圧縮タオルは乾いた状態で手のひらサイズのため、荷物を減らしたい温泉旅行や日帰り入浴に最適です。
水やお湯をかければすぐに展開し、フェイス用であれば洗顔後の拭き取り、ボディ用なら湯上がりの水分吸収までスムーズにこなせます。
特に注目すべき点は、衛生面でのメリットです。
タオルを使い回すと湿気による雑菌の繁殖が起こりやすく、カビ臭や肌荒れの原因にもなります。
使い切りの圧縮タオルであれば、こうしたリスクを低減できるため、衛生管理がしやすいのです。
日本衛生材料工業連合会の調査では、湿潤状態の布製タオルを24時間放置した場合、細菌数が10倍以上に増加するケースが報告されています。
この点からも、旅行や温泉などで使い捨てが可能な圧縮タオルの利便性は高いといえます。
ダイソーで販売されている温泉向け圧縮タオルは、ボディサイズの厚手タイプや吸水強化型などもあり、湯上がりの快適さを保つ工夫がされています。
パッケージには「肌にやさしい」「繰り返し使用不可」といった注意表示があり、使用目的を明確にすることでより効果的に使えます。
持ち帰り時も使用済みを個包装の袋に戻せば、湿気や臭いを最小限に抑えられます。
使い切りで衛生的、かつ軽量で持ち運びやすいため、出張や登山、スポーツ施設利用時などにも応用が利くのが魅力です。
100均の圧縮タオルの使い方と活用法ガイド

圧縮タオルは、持ち運びや保管がしやすく、衛生面でも安心できる便利アイテムです。
特に100均で手に入るタイプはコスパに優れ、旅行やアウトドア、防災備蓄まで幅広く活用できます。
しかし、「どうやって使うのが正解?」「体を洗うのは大丈夫?」「どんな種類を選べばいい?」といった疑問を持つ人も多いはず。
ここでは、圧縮タオルの正しい使い方や注意点、災害時の備えとしての利用法、ダイソーなどの製品を使った実用的な活用法まで詳しく解説します。
用途に合った選び方のポイントもあわせて紹介します。
圧縮タオルの基本的な使い方と注意点

圧縮タオルは、携帯性と衛生性を兼ね備えた便利な日用品として、家庭から防災備蓄まで幅広く利用されています。
使い方は非常にシンプルで、個包装から取り出し、常温またはぬるま湯に浸すだけで瞬時にタオル状へと戻ります。
特にぬるま湯(約35から40℃)を使用すると、繊維内部の膨潤が促進され、平均して20から30秒で柔らかく広がります。
この現象は、繊維の吸湿膨張特性によるもので、レーヨンやパルプなどの親水性素材ほど復元が速い傾向があります。
戻した後は軽く絞って水分量を調整し、フェイスケア、手拭き、清拭など目的に応じて使用します。
ただし、商品によってgsm(1㎡あたりの重さ)や繊維構造が異なるため、拭き取り用の薄手タイプでは強く擦ると繊維がほつれたり毛羽立ちが起きやすくなります。
特にメイク落としや洗顔後の拭き取りに使う際は、摩擦を抑えるためクレンジング剤を併用し、肌に滑らせるように扱うことが望ましいです。
また、再利用については衛生上の注意が必要です。
日本衛生材料工業連合会によると、濡れた繊維製品を24時間以上放置した場合、細菌数が10から20倍に増加することが確認されています。
このため、圧縮タオルは基本的に「一回使い切り」が推奨されます。
洗濯後の再使用も理論上は可能ですが、繊維の劣化や乾燥不十分による衛生リスクが高いため、あくまで使い捨てとして扱う方が安全です。
よくある疑問に対して、以下のポイントを整理しておきます。
よくある疑問へのヒント
・乾いたままでも使えるか:乾拭きは可能ですが、圧縮状態の繊維は硬度が高く、皮膚への刺激が強くなります。
軽く湿らせることで繊維が柔軟化し、肌あたりが格段に向上します。
・洗濯して繰り返すべきか:圧縮タオルの多くは再利用を前提にしていません。
使用後の繊維は水分を含むことで強度が低下し、次回使用時に破れやすくなるため衛生上も非推奨です。
・匂いが気になる場合:圧縮タオルは吸湿性が高いため、保管環境に影響を受けやすい製品です。
開封後はすぐに使用し、高温多湿を避けて保管すれば、不快臭やカビの発生を防ぎやすくなります。
これらの特性を理解しておくことで、圧縮タオルをより安全かつ快適に使用できるようになります。
特に肌への使用を目的とする場合は、素材と厚みを確認し、自分の肌質に合ったタイプを選ぶことが重要です。
災害時の圧縮タオルの使い方は?備えに最適

災害時は、清潔を保つための水や衛生用品が限られる状況に置かれます。
そのような場面で役立つのが、軽量・個包装で携帯しやすい圧縮タオルです。
1枚あたりの重量はおよそ2から5gと非常に軽く、50枚セットでも250g前後に収まります。
水を少量(50から100ml)加えるだけで使用可能なため、断水時にも簡易的な衛生維持が可能です。
用途は多岐にわたり、体拭きや顔拭きのほか、歯磨き後の口元ケア、赤ちゃんのおむつ替え時、介護現場での清拭、食器の簡易洗浄などにも活用できます。
特に乳幼児や高齢者のケアでは、使い捨てにすることで感染症リスクを抑えられる点が評価されています。
厚生労働省が公表する「災害時の生活支援物資リスト」でも、清潔保持用品の一つとして「使い捨てタオル類」の常備が推奨されています(出典:https://www.mhlw.go.jp/)。
保管方法としては、直射日光と湿気を避けることが最重要です。
外袋には多くの場合「品質保持期限」や「使用推奨期間」が印字されています。
これは製造時点の密封状態を基準にした目安であり、平均して3から5年の保管が可能です。
防災リュックや車載防災セットに入れる際は、湿気を防ぐためにジップ付き密閉袋や乾燥剤と一緒に保管すると品質を維持しやすくなります。
また、家族構成を踏まえた備蓄量の目安としては、「1人1日2枚×3日分+予備」を基準にすると安心です。
日常使用と兼ねたローリングストック方式(使った分だけ補充する備蓄法)を取り入れると、古い在庫を自然に更新しながら常に新しい状態を維持できます。
防災セットに組み込むコツ
・サイズを分けて入れる:ミニサイズは手拭きや口元用、フェイスサイズは体拭きに活用し、無駄を減らす。
・一緒に入れると便利な物:密閉袋、アルコールウェット、ゴミ袋、使い捨て手袋をセットにしておくと実用性が高い。
・アレルギー配慮:香料や漂白剤の有無を確認し、敏感肌の家族には事前に試しておくことで安心して使用できる。
このように、圧縮タオルは「軽量・省スペース・多用途」という三拍子がそろった防災アイテムです。
衛生的な生活を維持するだけでなく、災害時の心理的ストレスを軽減する役割も期待できます。
ダイソーのコンパクトタオルで体洗うのはOK?

ダイソーなどで販売されているコンパクトタオルを「体洗い用」に使うことは可能ですが、その適性を理解した上での使用が大切です。
圧縮タオルはあくまで拭き取りや清拭を目的として設計されており、ボディウォッシュとしての耐久性は限定的です。
素材構成を見ると、レーヨンやパルプを主成分とするものが多く、繊維の絡み構造が弱いため、強い摩擦や泡立てには不向きです。
体洗い用途に使う場合は、ボディソープをしっかり泡立て、肌表面を「なでるように」洗うのが適切です。
繊維表面の毛羽が立ちやすいため、こすり洗いは避けた方が安全です。
肌が敏感な方や子ども、高齢者は特に注意が必要で、柔らかいタイプ(gsmが低め)のタオルを選ぶと刺激を軽減できます。
また、衛生管理の観点からは、使用後の再利用は非推奨です。
湿った状態での保管は雑菌の繁殖リスクを高めるため、1回使用ごとに廃棄するのが望ましいとされています。
特に入浴施設やキャンプ場などで使用した場合は、温泉成分や皮脂が繊維に残留しやすく、洗っても完全に除去できない場合があります。
ボディ用として使うのであれば、一時的な代替品として非常に有効です。
旅行先や災害時、急な外泊など、タオルを持参できない場面では、軽量で衛生的な圧縮タオルが活躍します。
ただし、日常的な入浴用途には、専用のボディタオルや天然素材(綿・麻など)の製品を併用する方が肌への負担を軽減できます。
圧縮タオルの比較でわかる選び方のポイント

圧縮タオルを選ぶ際には、「どの場面で」「どの程度の頻度で」「どんな目的で」使うのかを明確にすることが最も重要です。
単純に価格の安さだけで選ぶと、用途に対してサイズや吸水性が合わず、結果的にコスパが悪くなる場合もあります。
以下では、製品選びの判断基準を技術的な観点から整理し、具体的にどのタイプを選ぶべきかを解説します。
まず「サイズ」は使用目的によって大きく異なります。
ミニサイズ(直径2から3cm程度、展開後約20×20cm)は手拭きやおしぼり用途に最適で、フェイスサイズ(約25×30cm)は洗顔後の水分拭き取りや簡易タオルとして活躍します。
大判サイズ(約30×60cm以上)は体拭きや清掃向けで、1枚で広い範囲をカバーできるのが利点です。
用途別に複数のサイズを常備しておくことで、無駄なく使い分けができます。
次に注目したいのが「素材」です。
一般的な圧縮タオルの素材には、綿(コットン)、レーヨン(再生セルロース)、ポリエステル、またはそれらの混紡があります。
綿は吸水性と柔軟性に優れる一方で乾きが遅く、レーヨンは乾きやすく衛生的ですが、濡れた状態では破れやすいという特徴があります。
混紡タイプはその中間に位置し、扱いやすさと耐久性のバランスが取れています。
製品パッケージの素材表示を確認し、自分の使用目的に合った繊維構成を選ぶことが重要です。
厚みは「gsm(grams per square meter)」で表され、数値が高いほど密度が高く厚みのあるタオルになります。
薄手(50から80gsm)は軽量で速乾性があり、携帯性重視に向いています。
中厚(100から150gsm)は一般的な拭き取り用途に最適で、厚手(180gsm以上)は体拭きや災害時の全身清拭に適しています。
このようにgsmを意識することで、用途に応じた強度と吸水力を見極めることができます。
また「個包装の有無」も見逃せない要素です。
個包装タイプは衛生面で優れており、バッグや防災セットへの収納にも便利です。
特に屋外利用や避難所での使用を想定する場合、密封状態が維持できる個包装タイプを選ぶと、湿気や汚染を防ぎやすくなります。
使用時の「戻しやすさ」は、実際の利便性に直結します。
製品によっては、水量50mlで20秒ほどで復元するタイプもあれば、100ml以上必要とするタイプもあります。
水を節約したい環境(災害時やアウトドアなど)では、少量で素早く戻るものを選ぶと効率的です。
製品パッケージに「復元時間」や「必要水量」の目安が記載されている場合は、購入前に確認しておくとよいでしょう。
最後に「価格」と「コストパフォーマンス」についてですが、圧縮タオルは1枚あたり10円未満から50円以上まで幅があります。
安価なものは素材が薄く破れやすい一方で、無印良品などの高品質タイプは吸水性・柔軟性・衛生表示の信頼性が高い傾向にあります。
使用頻度が高い方は100均製品で十分ですが、肌に直接使うフェイスケアや乳幼児の清拭には、素材表示が明確なブランド製を選ぶのが安心です。
以下の表に、選び方の主要観点を整理しました。
| 観点 | 着目点 | 目安の考え方 |
|---|---|---|
| サイズ | ミニ/フェイス/大判 | 使う部位と一度に必要な面積で選ぶ |
| 素材 | 綿/レーヨン/混紡 | 肌当たりと吸水性、乾きやすさを確認 |
| 厚み | gsmや層構造 | 拭き取り用は薄手、体拭きは中厚以上 |
| 個包装 | 有無と密封性 | 非常用・持ち運びは個包装推奨 |
| 戻しやすさ | 水量と所要時間 | 少量の水で数十秒なら携帯に向く |
| 価格 | 単価/枚数 | 使い切り頻度に合わせてコスパで判断 |
この比較から見えてくるのは、「シーン別の最適化」です。
日常生活の予備用途であればコスパに優れた100均製品が便利であり、防災や外出用には衛生面に優れた個包装タイプを選ぶと安心です。
一方で、日常的に肌へ直接使用する場合や、肌触りを重視する場合は無印良品などの品質重視モデルが適しています。
どの製品を選ぶ場合でも、「自分が使うシーン」と「必要な性能」を具体的に想定することが、失敗しない購入の最大のポイントといえます。
【まとめ】100均の圧縮タオルについて
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


