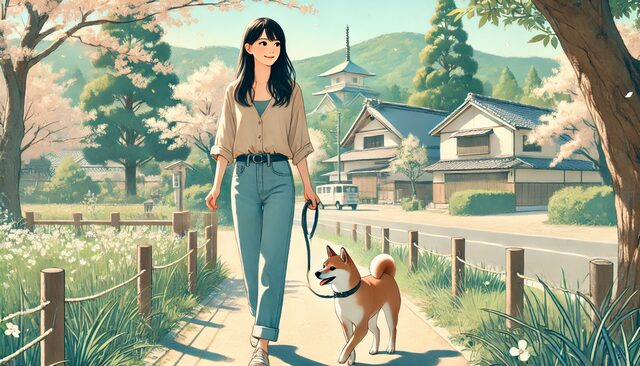グリーン車に犬を乗せたいと考えている方の中には、「どこまでOKなのか」「何がNGなのか」が曖昧で不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、グリーン車 犬で検索している方にとっては、料金のルールや「うるさい」と言われないためのマナー、そして長時間の乗車についての具体的な不安などがあるはずです。
本記事では、湘南新宿ライン・東海道新幹線・東海道線・中央線といった主要路線を例に、JRの規定や車内の注意点を詳しく解説します。
また、「新幹線で犬は断られた?」「新幹線で10キログラム以上の犬は大丈夫?」「犬を新幹線に5時間乗せてもいいですか?」といったよくある疑問についても丁寧にお答えします。
さらに、「ペットカートはJRで禁止されていますか?」というルールも含め、愛犬と快適に移動するための情報をわかりやすくまとめました。
■本記事のポイント
- グリーン車で犬を乗せる際のルールと条件
- 犬同伴時に必要な料金や切符の買い方
- 在来線や新幹線ごとの対応の違い
- トラブルを避けるためのマナーや注意点
グリーン車に犬の乗車ルールと料金を徹底解説

グリーン車に愛犬を同伴させたいと考えている方にとって、気になるのが「ルール」と「費用」です。
一般車両と比べて快適な空間が提供されるグリーン車ですが、ペットの同乗に関しても厳格な規定があります。
規定を知らずに当日トラブルになるのを防ぐためにも、乗車前に確認すべきポイントを整理しておくことが大切です。
ここでは、料金体系やキャリーの条件、さらには「静かに過ごす」ためのマナーまで、わかりやすく解説していきます。
グリーン車でも手回り品きっぷは290円必要

改札で犬を入れたキャリーケースを見せると、駅員が状態を確認したうえで「手回り品きっぷ」(290円)が発行されます。
これは新幹線だけでなく在来線でも同様で、ICカードや券売機では購入できず現金払いのみとなります。
まず結論を言えば、どちらの車両でもキャリーケース1つにつき290円の追加費用が必要です。
理由として、犬は荷物扱い(手回り品)となり、別途手続きを踏む必要があるからです。
具体的には、改札口でキャリーケースを駅員に見せ、タグ形式で発行されたきっぷをキャリーに取り付けます。
万が一、破損防止のために手提げや網棚に置いた場合でも、きっぷは提示できるよう携帯してください。
一方でデメリットとして、乗車前に有人窓口に立ち寄る必要がある点や、ICカード不可であること、改札の混雑時には列に並ぶ煩わしさがあります。
これらを踏まえ、電車利用の際は時間に余裕をもつことをおすすめします。
犬+キャリーは10kg以内・3辺120cm以内が条件

犬をキャリーに入れて電車に乗せるには、キャリーケースと犬の合計が10kg以内、かつキャリーの縦・横・高さの合計が120cm以内であることが必須です。
要件を満たしていれば問題なく乗車できますが、理由は車内のスペースや他の乗客への安全配慮があるからです。
具体的には、サイズや重さの境界を超えると持ち込み不可となり、当日の乗車が断られるケースもあります。
例えば、犬が大きくて10.5kgを超えていたり、キャリーが125cmだったりすると、改札で「規定オーバー」として拒否されてしまいます。
また、キャリーバッグは形が固定され、自立するタイプであることも求められています。
スリングや柔らかい布製バッグ、ペットカートは原則NGです。
ただし、分離できるタイプのペットカートであればケース部分を規定内にし、残りは手荷物として別扱いにすれば持ち込み可能です。
このようにルールが厳しくなっている理由は、他の乗客への配慮や安全確保のためです。
愛犬と快適かつスムーズに移動するには、事前に体重やキャリーサイズを正確に測り、JRの基準をしっかりクリアしておくことが重要です。
ペットカートは折りたたむ/分離必須

ペットカートを電車に持ち込む場合、カートとケースを必ず分離し、ケース部分が「縦・横・高さの合計120cm以内、かつケース+犬の重さが10kg以内」である必要があります。
その理由は、JRではペットがケースごと荷物として扱われるため、サイズや重さの制限を満たさなければ持ち込めないからです。
例えば分離できない一体型カートでは規定を超えるため、乗車不可となることがあります。
具体的には、まずカートからケースを外し、カート本体は折りたたんで荷物棚や足元に収納します。
実際にJR東日本の公式FAQでも「分離したカート部分は折り畳んで一般の手荷物として持ち込める」と明記されています。
注意点として、折りたたむ際に十分なスペースを確保できなかったり、荷物棚に入らない場合があります。
新幹線利用時は、特大荷物スペースつき座席の予約も検討しましょう。
旅行当日は予備時間を見て余裕を持って準備を行うことが望ましいです。
「うるさい」トラブル回避のためのマナー

電車や新幹線内で犬が鳴くと、周囲の乗客に迷惑をかけるうえルール違反につながります。
まず、犬はケースから出さず、吠えるようなら一度下車して落ち着かせることが推奨されています。
無理に静かにさせようと抱っこすると逃走のリスクがあり、そもそもケースから出すこと自体が禁止されています。
また、本来は事前にキャリー慣れや騒音への慣れトレーニングを行うことが大切です。
例えば自宅で電車の音を流しながらキャリーに慣れさせる方法や、短距離の試し乗車を繰り返しておくとストレスを軽減できます。
さらに、犬の安定を促すためにおやつやお気に入りのぬいぐるみをキャリー内に入れておく工夫も有効です。
ただし、噛みすぎて散らかすと衛生面で問題が生じる点に注意しましょう。
隣席の犬がうるさくて気になる場合は、自席の移動を検討、もしくは車掌へ静かに替えてもらえないか相談するといった対応も可能です。
何はともあれ、トラブルを避けるには「ケース内で静かに過ごす環境づくり」が基本となります。
グリーン車で犬との新幹線・在来線の比較と注意点

グリーン車で愛犬と移動する際には、「新幹線」と「在来線」でルールや対応が異なる点に注意が必要です。
どちらもペット同伴が可能ですが、車両ごとの制約や乗客との距離感、車内環境の違いによって気をつけるべきポイントも変わってきます。
さらに、ケースサイズや犬の体重によっては乗車自体ができないこともあります。
ここでは、実際に断られることがあるケースや、10kg以上の犬の場合の対応など、見落としがちな注意点を詳しく解説していきます。
東海道新幹線・湘南新宿ラインでの注意ポイント

東海道新幹線と湘南新宿ラインは、犬を同伴しての移動で特に以下の点に注意が必要です。
まず、新幹線では、ケースごと「手回り品きっぷ」(290円)を購入し、規定内サイズ・重量を満たしたキャリーに入れる必要があります。
JR東海でも同様のルールが適用されており、改札窓口でケースを見せることで購入可能です。
一方、湘南新宿ラインは在来線グリーン車での乗車においても、ケースから犬を出すことや顔を出すことは禁止されています。
つまり、常にケース内に完全に収納することが求められ、車内での行動も厳しく制限されます。
混雑する時間帯やドア付近の席は避け、最後部の座席など余裕のあるエリアを確保することが安心です。
乗車前には、各列車の乗り入れ状況や繁忙期の混雑予報も調べておくとトラブル防止になります。
東海道線・中央線での犬同伴ルールは?

東海道線や中央線といった在来線でも、犬の同伴にはJR東日本の規定が適用されます。
犬とケースを合わせた重量が10kg以内、かつケースの3辺の合計が120cm以下であることが条件です。
手回り品きっぷ(290円)は改札での購入が必要で、ICカードや券売機では扱われない点も共通しています。
また、中央線や東海道線では、通勤時間帯の混雑によりケースが乗客の足元や通路をふさぐ可能性があります。
そのため、事前に車両や時間帯を選ぶことが重要です。
加えて、乗車中は犬をケースから出さないこと、顔や手足を出さないことがルールとして徹底されています。
万が一他の乗客からクレームが入った場合、車掌が注意してくれますが、状況によっては次駅で降ろされることもありますので注意が必要です。
このように、在来線でも快適かつトラブルなく犬を同伴するためには、時間帯・車両の選択、ケースのサイズ・使い方、そしてマナーの徹底が不可欠です。
新幹線で犬は断られた?主な理由と対処

新幹線でペットの愛犬が乗車を断られる主な理由は、大きく分けて「規定違反のキャリー」「騒音や臭いによるトラブル」などです。
例えば、キャリーに犬と飼い主が思っていたより重く、規定の「ケース+犬で10kg以内、三辺合計120cm以内」をオーバーしてしまうと、駅員にストップされ乗車が拒否されることがあります。
また、出発後に「吠え続ける」「臭いが強い」と苦情が来れば、途中駅で降ろされる可能性も出てきます。
そこでおすすめなのが、「事前準備」と「駅員に相談」です。
出発2から3週間前にはキャリーで自宅トレーニングをして、車内放送の音や振動に慣れさせましょう。
さらに乗車前に駅窓口や改札で、キャリーや犬の状態を係員に見せ「これで大丈夫か」を確認しておくと、当日の不安を減らせます。
荷物が規定サイズを超える場合は、新幹線よりペット輸送サービスや車移動を検討するのも賢い選択です。
新幹線で10キログラム以上の犬は大丈夫?

犬とキャリーの合計が10kgを超えると、新幹線の「手回り品」として持ち込めなくなるため、基本的には乗車できません。
特に中型犬以上の場合、規定サイズに収めることが困難なため、キャリー選びでもうまくいかないケースが多いです。
ただし盲導犬・介助犬・聴導犬などの補助犬については例外で、認定された犬はケースに入れなくても無料で乗車可能です。
それ以外の犬を10kg以上で新幹線に乗せたい場合は、代替案を検討する必要があります。
例えば、ペット専門の輸送業者による温度・ストレス管理付きの輸送プランがあり、自宅から目的地まで安心して預けられる選択肢があります。
あるいは、犬と一緒にマイカーでの移動や、飛行機貨物での移送も考えておくと実用的です。
【まとめ】グリーン車で犬について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。
- グリーン車でも犬はキャリーケースに入れる必要がある
- キャリーケースは三辺の合計が120cm以内であること
- 犬とキャリーの合計重量は10kg以内に制限されている
- ペット同伴時は手回り品きっぷ(290円)の購入が必要
- 手回り品きっぷはICカードでは購入できず現金のみ対応
- キャリーは形がしっかりした自立型が原則である
- ペットカートは分離・折りたたみが必須条件とされている
- 分離したカート部分は通常の荷物扱いとして持ち込める
- 吠える犬は乗車後にトラブルの原因となることがある
- 鳴き声対策には事前のトレーニングが効果的である
- 車内では犬をキャリーから出すことは禁止されている
- 東海道新幹線でも湘南新宿ラインでもルールは共通
- 中央線や東海道線では混雑時間帯を避ける工夫が必要
- 新幹線で断られる理由は主にサイズオーバーや騒音による
- 10kg以上の犬は新幹線に原則乗せられず代替手段が必要